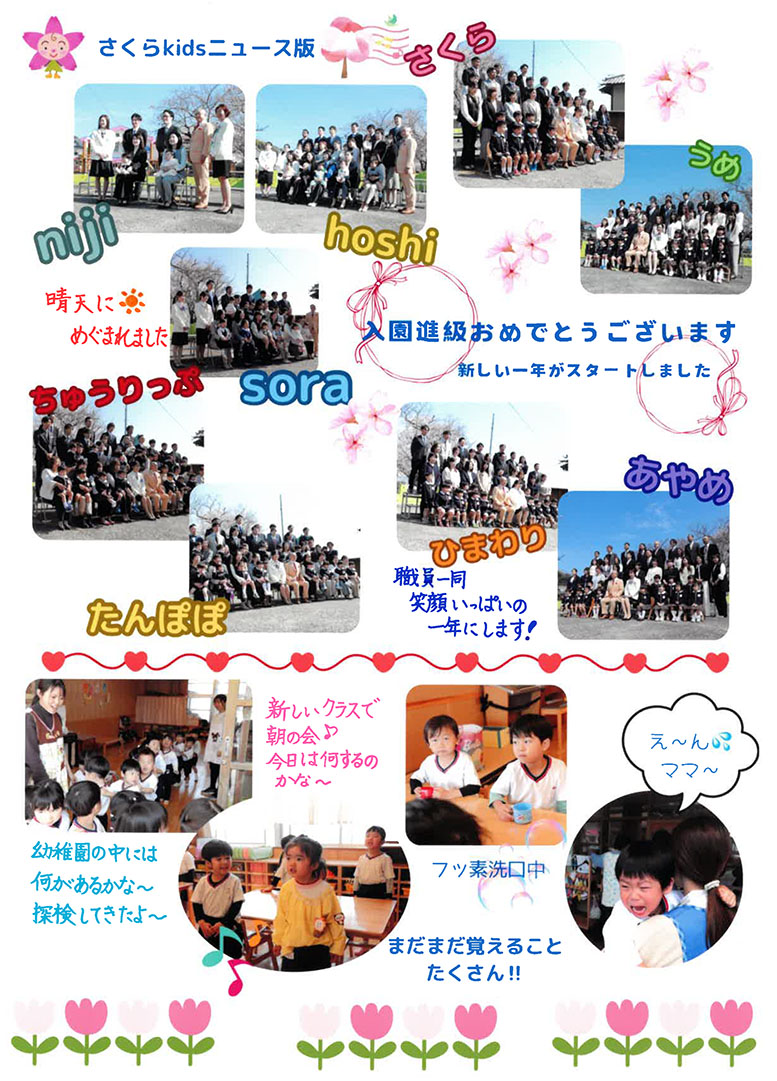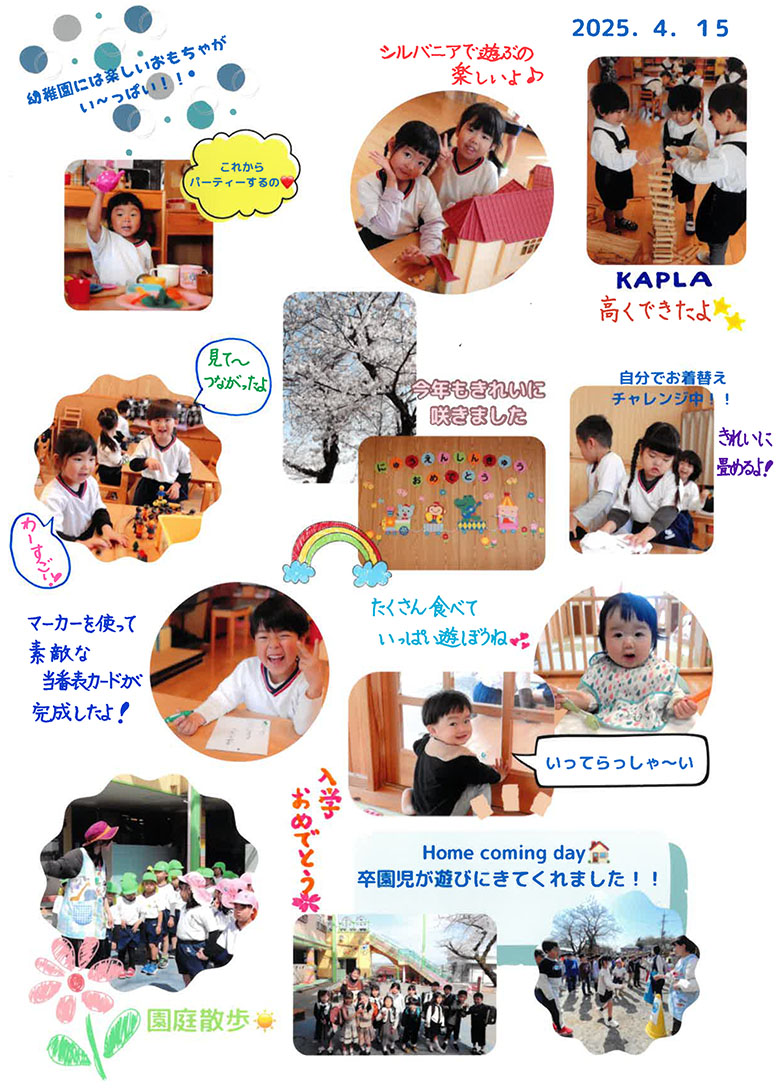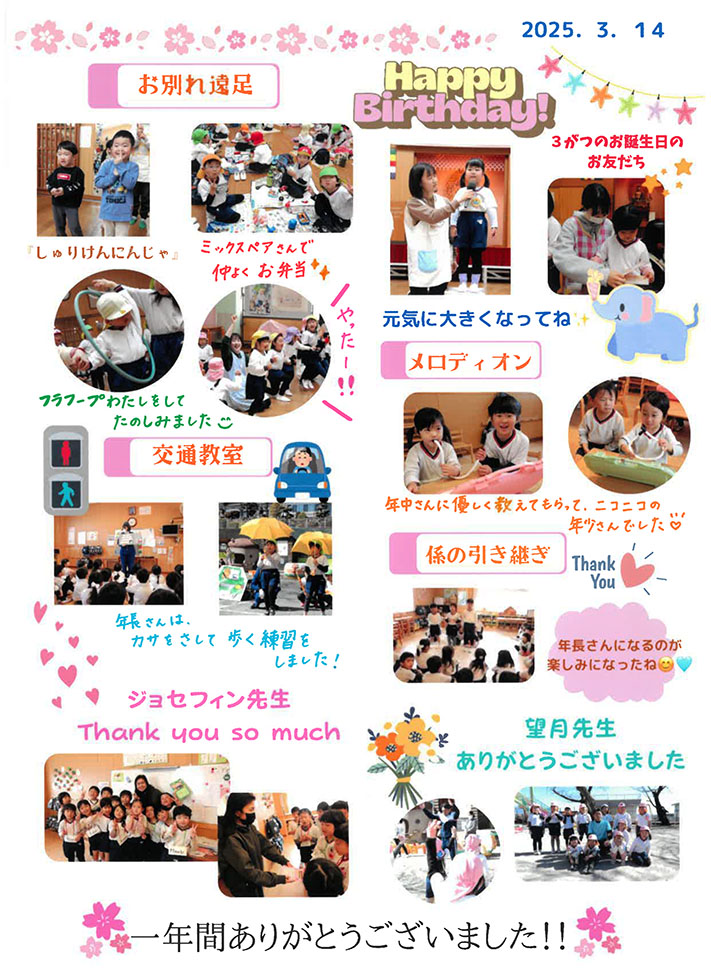おうちの方のご感想(卒園編)
2025.04.07(月)
●あっという間に幼稚園での3年間が経ちました。卒園式が始まる前のビデオを見て、年少さんから今までの事を振り返り涙が出てしまいました。
卒園証書をもらう時、親が立ってもいいという先生方の配慮のお陰で、帽子を被った可愛い姿.お辞儀をしてしっかり証書をもらう格好いい姿を見る事が出来て嬉しかったです。主人は、内容の濃い卒園式でよかったと言っていました。私もそう思います。
園長先生、先生方、今までありがとうごさいました。心温かい素敵な卒園式をありがとうごさいました。
さくら組男の子のお母さん
●年長さんの一年、過ぎてみれば本当にあっという間でした。子供が幼稚園生活を楽しんだのと同様、私も年間通じての様々な行事を楽しませていただきました。どれも素晴らしい思い出として記憶に残っています。これも先生方の入念な準備と愛情を持った根気あるご指導の賜物だと感謝しております。
四年間、大変お世話になりました。ありがとうございました。毎年の同窓会を楽しみにしております。
うめ組 女の子のお父さん

●感動の卒園式をありがとうございました‼5年間初めての集団生活をさくら台幼稚園で過ごせて本当に良かったです。あっとゆーまの5年、たくさんの経験をさせて貰い園長先生をはじめとする先生方、幼稚園関係者の皆様に優しさと愛情いっぱい貰って成長してきたんだなと感謝の気持ちでいっぱいです。さくら台幼稚園では、普段の生活の中でこれから大人になる上で必要な事をしっかりと教えて下さり先生方は大変なご苦労があったかと思いますが、人の気持ちを考えられる優しい子に成長してくれました。
1人1人の個性を大切にしてくれるので苦手な事も大変な事も一度も弱音を吐くことなく幼稚園に通う事が出来ました。大変な事も先生やお友達と励まし合いながら成長できる本当にいい環境だったと思います。行事を通すことでお友達と助け合い協力する事でクラスに団結力が出来、最後の1年はその成長が一番輝いたと思います。さくら組さんとうめ組さんが一つになり奏でる合奏や鼓隊、合唱、組み立てもリレーも本当に素晴らしかったです。
成長は大変嬉しいですが毎朝いってらっしゃい、お迎えの時にはお帰りなさいと声を掛けて下さる先生方、それがあたしの毎日の当たり前になっていたので、さくら台幼稚園を離れるのは本当に寂しくてならないです。安心して仕事をしながら子育て出来たのは先生方のお陰です。そしてさくら台幼稚園が大好きです。本当にありがとうございました。
さくら組 女の子のお母さん
●ついに卒園。年長になり、一つ一つの行事が終わってしまう寂しさを感じながらも、子どもたちが毎回成長していく姿を見ることができ、感動し、何度も涙してしまいました。
身体も心も大きく成長でき、嬉しく思います。家から離れている幼稚園に預けることは不安もありましたが、さくら台幼稚園に通うことができ、本当に良かったです。
この3年間はかけがえのない素敵な時間を過ごすことができました。先生方には心から感謝しております。本当にありがとうございました。
さくら組 女の子のお母さん
おうちの方のご感想(進級編)
2025.04.07(月)
●日々子供の成長を感じているのですが、特にコミュニケーション能力がぐんぐん伸びている事をとても実感しております。それはやはり園で先生方が毎日丁寧に子供に接して話かけてくれているからだと思っております。これまで子供に関わってくれた先生方にはとても感謝しております。これからもよろしくお願いいたします。
たんぽぽ組 男の子のお母さん
●年少さんの頃、毎朝ママと離れたくないと泣いている姿ばかり見ていたので、年中さんは大丈夫かなぁ…ととても心配していたのですが、年中さんに進級したらケロッと泣かなくなり、なんで泣かなくなったの?と聞くと『先生が優しくて大好きだから!』とニコニコと登園するようになりました。娘から聞く先生方の話は、いつも優しく温かな言葉で娘を包んで下さり、『先生がいるから幼稚園に行く!』と先生方の存在が娘の何よりもの原動力となりました。
泣き虫な娘でたくさんご迷惑をおかけしてしまいましたが、先生方のおかげで大きく成長できました。1年間本当にありがとうございました。
ひまわり組 女の子のお母さん
●入園当時はまだハイハイやつかまり立ちで赤ちゃんという感じだったのに、今はしっかり歩いて、時には走ったりして、言っていることを理解したり、自分で出来ることが増えたり、大きく成長した一年だったなと感じています。一年があっという間でした。こんなにも成長したのは、先生方が愛情を持って接してくださったおかげです。
入園した当時は幼稚園で過ごす事できるかな、給食食べられるかな、お昼寝できるかななど不安でいっぱいでした。ですが、お迎えに行くと、笑顔で駆け寄ってきてくれて、きっと楽しく過ごせているんだな、大丈夫そうだなと言うのが伝わり、不安も段々と解消されていきました。また、お迎えの際の先生方とのちょっとした会話や連絡帳に園生活の様子を書いて下さり、不安が解消されました。毎日連絡帳を読む事が楽しみで仕方がありません。hoshi組さんになってどんな成長するのか今からワクワクしています。
先生方、一年間ありがとうございました。
niji組 男の子のお母さん
●あっという間の一年間で、我が子の心も体も成長できました。先生方も大変な中子供たちと関わっていただき感謝しております。一親として、先生方の休息も大切にしてほしいと思います。一年間本当にありがとうございました。
ちゅうりっぷ組 女の子のお母さん

●年中さんになり、出来ることが沢山増えました。本人もそれが嬉しく、また自信に繋がっていました。朝登園すると毎日お友達が寄ってきてくれたり、お迎えに行くと先生が今日の出来事をお話ししてくれたり、そんな温かい幼稚園に出会えて幸せですし、感謝の日々です。
幼稚園生活最後の一年、ますますの成長を楽しみにしています。そしてあっという間に過ぎてしまう日々をしっかり噛み締めながら息子を見守っていきたいと思います。ありがとうございました。
ひまわり組 男の子のお母さん
●初めての保育園で不安もありましたが、どの先生も優しく接してくださり、親子共にだいぶ慣れました。今では登園すると、泣かずに当たり前のように先生やお友達のところへ行きます。いろんな経験をさせていただき沢山成長を感じられる1年でした。ありがとうございました。
niji組 男の子のお母さん
●1歳になる前に入園し不安でいっぱいでしたが、そんな不安を吹き飛ばすほど毎日元気に笑顔で通ってくれて、ありがとうの気持ちでいっぱいです。短い間でしたが、いろいろな経験をさせて頂いてありがとうございました。
niji組 男の子のお母さん
●年少さんのときは行きたくなく、制服に着替えず、困っていましたが、今は幼稚園毎日いきたいと土日もいっているほどです!行事に参加するたび娘の成長した姿をかんじます!一番に年中さんになって成長したのは絵です!今では毎日、動物や人など描いてとても絵を描くのが好きなようです!去年から働き始め最初は寂しくならないかなと思っていましたが、友達や先生と毎日楽しそうで安心して預けられました!ありがとうございます!来年はついに園で一番大きい年長さん、本人も何組さんになるかなとワクワクドキドキしています!
ひまわり組 女の子のお母さん
●途中入園で短い間でしたがありがとうございました。歌が好きで幼稚園で習った歌を聞かせてくれる事があったり先生とこういうお話をしたよと教えてくれる事がありました。最後の方は中々、幼稚園に1日行ける日がほとんど無く先生方にもご迷惑をお掛けしてしまう事がありましたが毎日、行く時に優しく「おはよう」と声を掛けてくださったり幼稚園に行く気持ちを盛り上げて下さり、とてもありがたかったです。
次の学年でも好きな事をみつけ楽しく通えたらと思います。本当にありがとうございました。
ちゅうりっぷ組 男の子のお母さん
●ついこの間まで年中さんになれるのかなと不安に思ってたことが嘘のように、1年の間でとても成長してくれたと思います。制服登園になり初めは朝の支度にてんやわんやでしたが、いつのまにかママとお支度競争ができるほどになりました。
毎日の遊びの内容も少し頭を使ったゲームになってそのことを詳しく話してくれたりとお話も上手になりました。幼稚園行きたくないなと登園した日も、大好きな先生におはようと言われると照れながら嬉しそうに教室に入って行けて安心しました。今年度も元気に楽しく通ってくれてよかったです。先生方のおかげです。4月から憧れの「上」に行けるのでどんなお兄さんになれるか楽しみです。
ひまわり組 男の子のお母さん
●先生方、1年間大変お世話になりました。今年はお姉さんになろうと一生懸命がんばる姿がたくさん見られた一年でした。家では思い通りにならなくて、すねたり、甘えたり、イヤイヤ言ってしまったりする時もありましたが、幼稚園に行けば先生や友達がいつも通り温かく接してくれて、そこにいつも娘の居場所があったので、毎日の幼稚園を楽しみに1年間、前向きに過ごすことができ ました。
昨年に比べると幼稚園での出来事を話せるようになったり、友達と遊べるようになったりと、大きな成長も感じました。(今日は何やったの?)と聞いてもすぐに忘れてしまうようで、よくわからないこともまだまだ多いですが、連絡帳の先生のメッセージを読むといつも嬉しそうに話してくれました。またさくら台の動画にsora組の先生や友達が映ると自分のことの様に喜んでいて、(こなちゃんの先生!こなちゃんの友達なんだよ!)と何度もアピールしてくれました。
お忙しい中で、貴重な経験をたくさんさせていただき、また楽しい思い出をたくさん作ってくださり、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。
sora組 女の子のお母さん
●hoshi組さんになり、まず驚いたのはトイレでおしっこができるようになったことです。まだおむつは外せないものの成功した時は子供の成長を感じずにはいられませんでした。言葉も沢山覚えて自分で考えて使っている様子も見られ、友だちも増え、私に友達の名前を教えてくれたりもしました。イヤイヤして困ったりもしましたが、先生方に「焦らなくていいですよ」「大丈夫ですよ」など声をかけていただき、安心して成長を見守ることができました。いつも明るく迎えていただき、親子共々感謝しています。「幼稚園楽しい!幼稚園行きたい!」と子供が毎日のように言っているセリフです!これからもよろしくお願いします。
hoshi組 男の子のお母さん

●この一年で幼児さんへの仲間入りに着実に近付いていくのがよく分かりました。身体の成長だけでなく、自分で!の気持ちや色々な事への興味関心が高まり、親としては嬉しい反面「もう、赤ちゃんではないんだなぁ」と、少し寂しさを感じる事もありました。ついつい赤ちゃん扱いをしてしまいがちですが、園では着替えや食事等、自分でなんでもやっているようで…。先生方のサポートやお友達からの刺激を受けて、日々学んでいるんだなと感じます。園であった事を楽しそうに報告してくれる毎日です。先生方にはいつもお喋りな息子を優しく見守って頂き、感謝しております。
年少さんへの憧れや不安も感じているようですが、変わらずにのびのびと過ごしていけると良いなと思います。今年度も大変お世話になりました。ありがとうございました!
sora組 男の子のお母さん
●入園してから1年間、いろいろと教えて頂いてありがとうございました。入園してすぐの頃は毎日泣いてばかりで、給食を一口しか食べられない日もあり、このまま通うことができるのかとても不安でした。でもだんだん慣れてきて、途中からはお友達と同じ量の給食を完食出来るようになり、帰宅すると園での様子をうれしそうに話してくれるようになりました。
運動会では、大きな声でお返事をしてとても楽しそうでした。リズムの会では、大勢の人の前で緊張して歌を忘れたりしないか心配していましたが、最後まで大きな声で歌って、上手に踊ることも出来ていました。ひとつの行事を終えるたびに成長している姿を見ることが出来ました。
今では自分で好きな洋服を選び、着替えもひとりで出来るようになり、うがいもとても上手になりました。お友達とも仲良く遊べるようになり、毎日楽しそうに通っています。たくさんのことを教えて頂いた先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。4月からは年少さんになりますが、これからもどうぞよろしくお願い致します。
sora組 女の子のお母さん
●年中からの転園となり、新しい環境に慣れるまで時間がかかる子なので、大変心配しておりました。そんな親の心配をよそに、すぐにお友だちと仲良くなり、幼稚園楽しい!先生もお友だちも大好き!と元気いっぱいに通う様子に、とても安心したことを覚えております。元々保育園だったこともあり、あまり保護者が関わる行事が多くありませんでしたが、この1年でさまざまな行事を通して幼稚園での生活・周りとの関わり方を実際に見ることで、今まで以上に成長を感じられたと思います。まったく跳べなかった縄跳びも、拙いながら前跳 び・後ろ跳びが出来るようになっていて驚きました。また、行事のDVDがお気に召したようで、暇さえあれば見ています。
本当に1年間ありがとうございました。来年度もよろしくお願いいたします!
あやめ組 男の子のお母さん
●そら組さんになってから、いつの間にか泣かずに行くようになり、いつの間にかスムーズに幼稚園での送り迎えができるようになりました。
思い返せばこの1年で色々なことができるようになり、本当に成長を感じます。恥ずかしがり屋の息子は人前に立つことが苦手で、リズムの会は心配していましたが、堂々と踊ったり歌ったりする姿を見て、感動しました。日々の練習で自信をもたせてくれた先生方、本当に感謝しております。
来年度から年少さん、今後の成長も楽しみです。
sora組 男の子のお母さん
●この1年間で沢山の経験を経て体も心も成長しました。運動会、リズムの会など人前に立つ緊張感。完璧主義な娘はプレッシャーの中、様々な感情を抱いたことだと思います。ですかその感情をまだ上手に受け入れてられない部分も多く、娘自身も戸惑うことがほとんどでした。それを親である私たちが理解してあげられなかったのは娘に申し訳なかったなと思います。そんな中でも一生懸命頑張ってくれた娘には感謝しかありません。そしてそんな娘を支えてくれた担任の先生も本当にありがとうございました。4月当初から娘の性格を十分に理解して下さり、安心して幼稚園に通わせることができました。お友達との関わりでも多くの事を学んだ一年で、時には悲しい思いをした時もありましたがそのような経験を経て今では大好きなお友達もできたようです!
全ての経験が今の娘を作っています。その経験をさせてくれた幼稚園の先生方、本当にありがとうございました。
ちゅうりっぷ組 女の子のお母さん
●家でも先生の名前とお母さんを言い間違えるほど大好きな先生♡1年間ありがとうございました。甘えん坊で手がかかる子だったと思いますが、熱心に指導して下さって本当に感謝です。たくさんのイベントを通して親も素敵な思い出が出来ました。子供にとっては毎日色んな経験をさせてもらい楽しい時間を過ごせていたと思います。担任の先生以外の先生、職員さんも優しく接してくれて本当に楽しい場所なんだと感じます。
この春からは下の子も入園します。ずっと楽しみにしていた幼稚園に行けると大喜びです。ヤンチャな2人ですが……よろしくお願いします。
ひまわり組 男の子のお母さん
●年中さんの1年間、お世話になりました。途中、泣きながら通っていた朝もありましたが、今ではバイバイと笑顔で登園できるようになりました。いつも優しく迎えてくれた先生のおかげです。ありがとうございました。
その他にも、プールや楽器、オペレッタ、マラソン、縄跳びなど、できることが増えて充実した1年でした。できなくて悔しい気持ちや、負けたくない気持ち、できるようになり楽しい気持ち、みんなとやった達成感、たくさんの成長を側でみることができました!
年長さんでの成長もすごく楽しみです。応援を頑張りたいと思います。ありがとうございました!
ひまわり組 女の子のお母さん
|
|